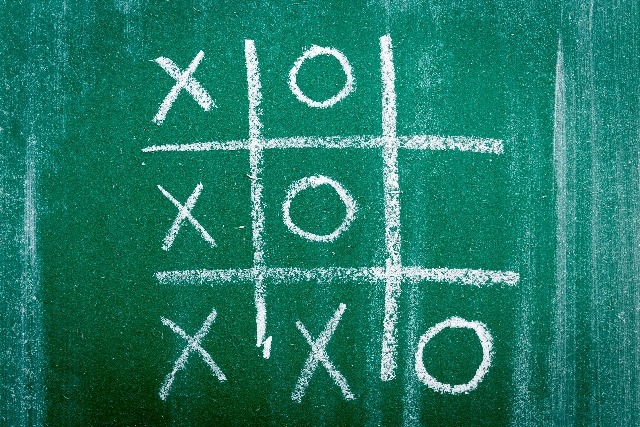クインティリアヌスの先見性
実は、睡眠によって記憶が定着するということを提唱したのは、エビングハウスら科学者たちではありません。クインティリアヌスという、「弁論家の教育」などの著作で知られる古代ローマ帝国の修辞学者が、今から2000年以上も前に次のように書き残しています。
「うまく繰り返すことが出来なかったことも、翌日には容易に出来るようになっている。睡眠という、一見健忘を引き起こすと思われているときこそ、記憶を強化しているのだ」
クインティリアヌスのこの言葉は、特に楽器やスポーツなどの経験がある方なら、すぐにピンと来るのではないでしょうか。必死に練習してもなかなか上手くならなかった身体の動きが、数日後には、たとえそのあいだ練習をしていなかったとしても、驚くほど上達していることに気づいた…、そんな経験をお持ちの方もたくさんいらっしゃると思います。これは、まさに睡眠による記憶強化の働きのおかげです。
記憶の種類
記憶にはいくつかの種類がありますが、簡単にまとめると、次のように分類することが出来ます。
宣言的記憶(陳述記憶)
宣言的記憶は、陳述記憶という別名が表すように、言葉として記したり話すことの出来る記憶のことを指し、さらに次のふたつに分類される。
- エピソード記憶 … 時間や場所など、個人的に体験した出来事にまつわる記憶で、文章として記述出来るもの。さらに、エピソード記憶のなかでも場所にまつわる記憶を空間記憶と呼び差別化することもある。
- 意味記憶 … エピソード記憶とは異なり、個人的に体験した出来事に限らない、一般的な事柄にまつわる記憶。行ったことのない場所や、会ったことのない人の名前でも、知識として知っている事柄は意味記憶となる。
非宣言的記憶(非陳述記憶)
非宣言的記憶は、こちらも非陳述記憶という別名が表すように、言葉として記したり話すことの出来ない、身体が覚えている技能や感情のことを指し、さらに次のふたつに分類される。
- 手続き記憶 … 言葉で表現することの出来ない、運動能力や技能にまつわる記憶。楽器の演奏、スポーツの技術、日常の動作など、特に意識せずにしている行動や技術を指す。
- 情動記憶 … 恐怖、不安などの感情にまつわる記憶。論理的なものではなく、より本能的なものなので言葉で表現することが難しい。睡眠障害や精神疾患と深い関連があると考えられている。
宣言的記憶と実験の厄介な関係
実際のところ、宣言的記憶と非宣言的記憶は、その成立のメカニズムや内容が大きく異なるため、一概に「記憶」として両者と睡眠との関わりを論じることには、多少難しい面もあります。
たとえば、前回、前々回と見てきたいくつかの実験は、いずれも宣言的記憶に関するものでした。もちろん、睡眠によって宣言的記憶が強化されることも多くの実験によって証明された事実です。しかし実際には、睡眠と記憶の関係についての実験では、非宣言的記憶のほうが多く用いられます。これには、宣言的記憶の性質が大きく関係しています。
言葉として話し、記述することが出来る宣言的記憶は、意識的な作業が必要となってくるため、被験者個人の資質やその日の集中力、実験の際の環境などによって左右される要素も大きくなってしまい、正確な評価を導き出すことが難しい場合が多々あるのです。
まして、睡眠は集中力と大きな関係があるため、実験結果の評価はさらに難しいものとなります。そのため、睡眠と記憶の関係を探る際には、非宣言的記憶を用いることが多い、ということです。では、実際に非宣言的記憶を用いた実験には、どのようなものがあるのでしょうか。
練習のあとには眠ること
イスラエルのワイツマン研究所の研究チームが考案した、視覚弁別課題と呼ばれるテストは、非宣言的記憶を用いた実験の、もっとも分かりやすい例です。このテストは、不規則な絵柄のなかから、ある一定のパターンを認識する速さを測定するもので、若い健康的な男女を対象者に実験が行なわれました。実験の結果、集中的にテストを繰り返すとパターンを認識するまでの時間も短くなりますが、睡眠をとった翌日になると、さらに一層成績が向上していました。
アメリカ、ハーバード大学の研究チームが行なった実験も、非宣言的記憶を用いたものです。こちらはさらに簡単なもので、パソコンのキーボードのタイピング課題を使用したものでした。実験の結果は、ワイツマン研究所の実験と同じように、繰り返しの練習によってタイピングは一定の水準まで上達したが、練習後の睡眠を経ることでさらに著しい技術の向上がみられた、というものでした。研究チームはこの結果を受けて、「新しい身体的技能を習得するためには、練習をしたその日に6時間から8時間程度の睡眠をとることが欠かせない」という研究結果を発表しました。
非宣言的記憶を用いたその他の実験
非宣言的記憶を用いた実験は、他にも数多く行なわれています。簡単に並べてみると…
- 様々な図形がランダムに現れるモニター上に、ある特定の図形が現れたときだけ、被験者にスイッチを押してもらい、その反応速度を測定する。
- テトリスに代表される、比較的単純なテレビゲームを初心者にプレイしてもらい、その上達のスピードを測定する。
- モニター上に現れた図形を、手許にあるタッチパネルをペンでなぞる速度を測定する。タッチパネルには細工が施されていて、モニター上の図形を90°回転させた形でなぞると正確になぞれるようになっている。
いずれの実験の場合にも、被験者は練習の後に睡眠をとるグループと、睡眠をとらないグループに分けられ、前者のグループのほうに明らかな技術の向上が見られました。
これらの実験はすべて、非宣言的記憶のうち、手続き記憶を用いたものです。睡眠は、どのようなメカニズムによって手続き記憶を強化するのでしょうか。また、もうひとつの非宣言的記憶である、情動記憶は、睡眠とどんな関係にあるのでしょうか。
Lesson 5-3 まとめ
宣言的記憶…言葉として記したり話すことの出来る記憶のこと。
- エピソード記憶 … 時間や場所など個人的に体験した出来事にまつわる記憶で、文章として記述出来るもの。場所にまつわる記憶は空間記憶と呼ぶこともある。
- 意味記憶 … 個人的に体験した出来事に限らない、一般的な事柄にまつわる記憶。
非宣言的記憶…言葉として記したり話すことの出来ない、身体が覚えている技能や感情のこと。
- 手続き記憶 … 言葉で表現することの出来ない、運動能力や技能にまつわる記憶。楽器の演奏、スポーツの技術、日常の動作など。
- 情動記憶 … 恐怖、不安などの感情にまつわる記憶。論理的なものではなく、より本能的なもの。
新しい身体的技能を習得するためには、練習をしたその日に6時間から8時間程度の睡眠をとることが欠かせない。